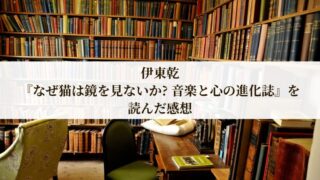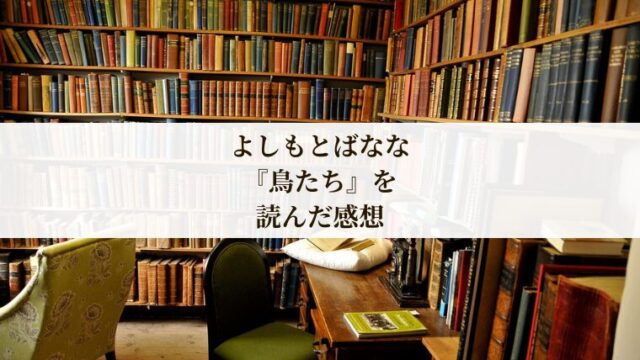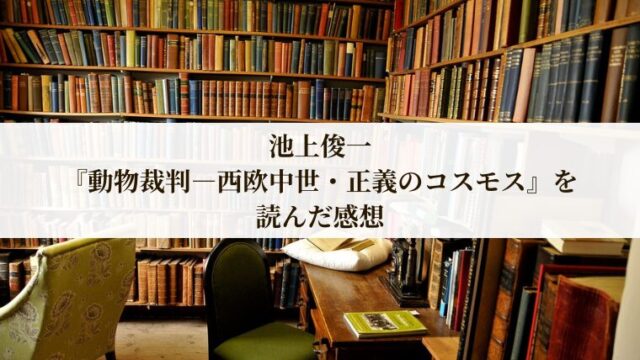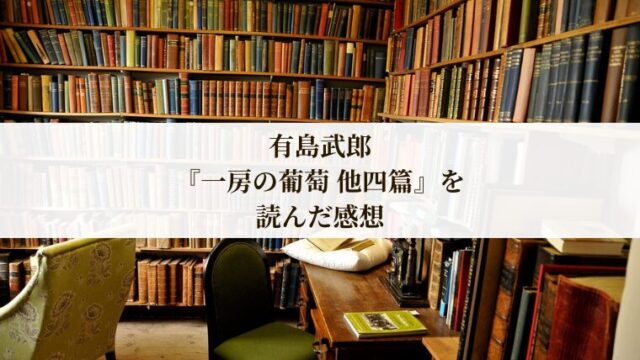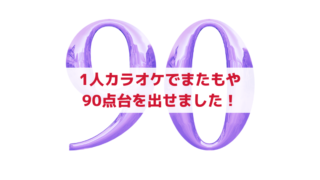伊東乾『指揮者の仕事術』を読んだ感想
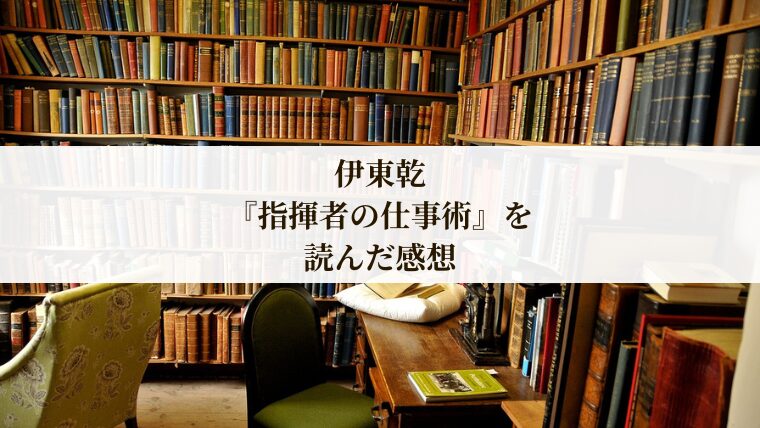
皆様こんにちは、霜柱です。
伊東乾さんの『指揮者の仕事術』(光文社新書)を読みました。
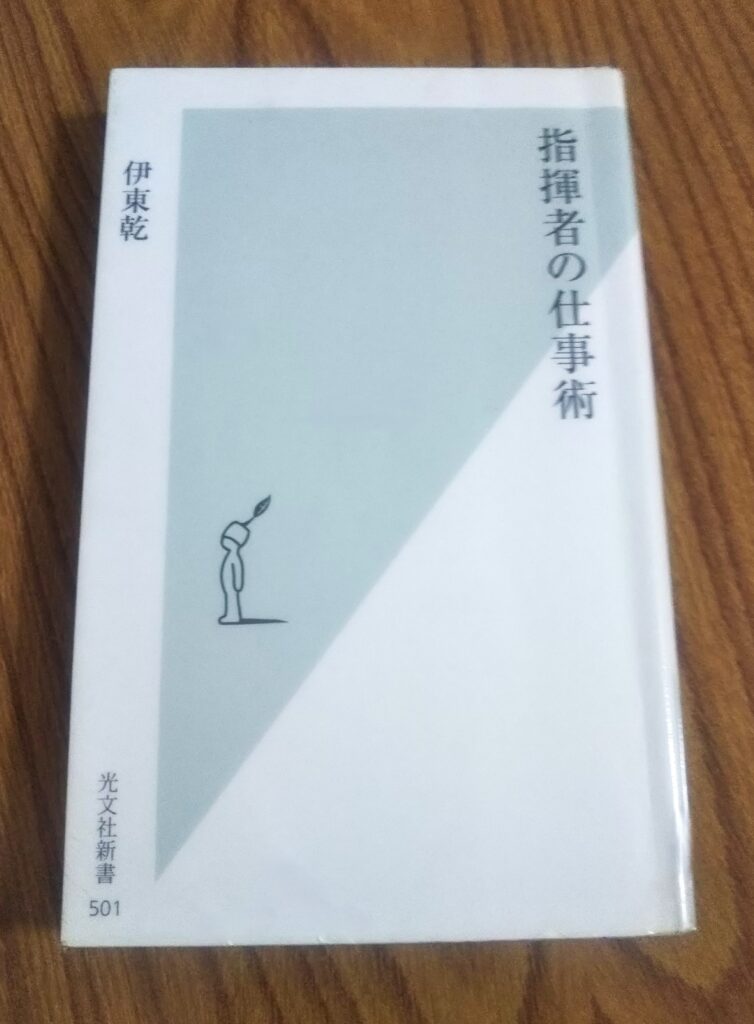
早速、読んだ感想を書いていこうと思います。
感想
指揮者は経営者みたいな存在
指揮者って言葉はよく聞きますし、オーケストラでも指揮棒を振っているので存在感もあると言えます。ただ、「指揮者って具体的にどういう存在なのか?」「もし指揮者がいなかったら?」等、そういった疑問があるのも事実です。
指揮者はいなくても成り立つ事は成り立つらしいです。ですが、指揮者がいればどの様に演奏したら良いか明確に判断出来ますし、全体も纏まる事が出来ます。
また、誰が指揮をするかで音が全く変わる様です。
指揮者は経営者、社長、監督の様な存在なのですね。
確かにこの点は会社とかでも似ているかもしれません。優れた経営者や監督なら会社やチームを良い方へ導けるでしょうし、そうでなかったら悪い方向へ行ってしまうでしょう。
指揮について「そうなのか!」と思える事が載っていたので、それが読めて面白かったです。ただ、指揮以外の話も多かったので、本のタイトルと中身が一致している様なしていない様な・・・という印象も正直受けました。でも、指揮以外の話も興味深かったです。
指揮以外の話
伊東さんとレナード・バーンスタインの出会い、バイロイト祝祭劇場の「奈落」についての話、ヨーロッパでベートーヴェンの「第九」は何故頻繁に演奏されないのか? など、興味を引く話も読めて良かったです。
日本では年末に「第九」を歌うイメージがとても強いですが、この曲は歌詞や音楽の意味がとても難解との事。私は「第九」の歌詞を全然知りませんが、この辺りは日本人とヨーロッパ人では解釈や姿勢に差があるのかもしれないと感じました。
他に「そうなんだ!!」と驚いたのは、人間は片耳だけで知的な音声言語を認知しているという事です。例えば電話は片耳だけで聞いていますが、これを両耳で聞いたら、ちゃんと認知出来ない様です。
こういう事は私の人生において今まで全然考えた事がありませんでした。人間の耳って、そう考えると不思議なんですね。
音楽大学なら指揮を学べる学科があると思いますが、フランスのパリ国立音楽院の指揮者養成方法はビックリしました。「修羅場を山ほど経験させる」やり方らしいです。私なら1日と持ちませんね(笑)。
簡単なまとめ
『指揮者の仕事術』というタイトルですが、それ以外の話も色々載っています。知らない事ばかりだったので、読んでいて学びが多かったです。
ただ、指揮者に完全にフォーカスしている訳ではないので、「指揮者に関する事だけ読みたい!」という人には微妙に感じるかも。
指揮者を含めたオーケストラの音楽や舞台に興味がある人なら、面白く読めるのではないでしょうか。