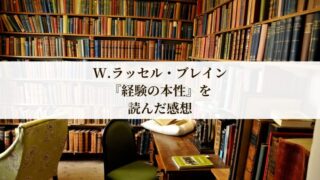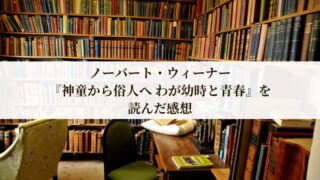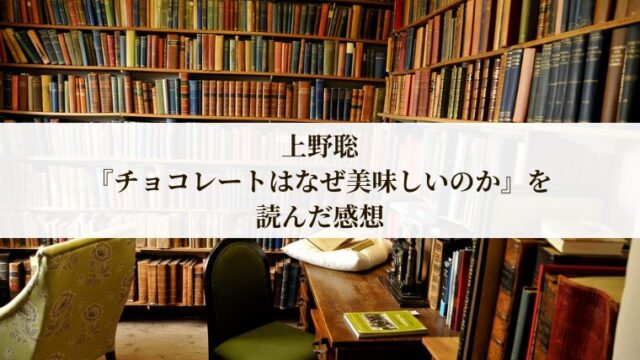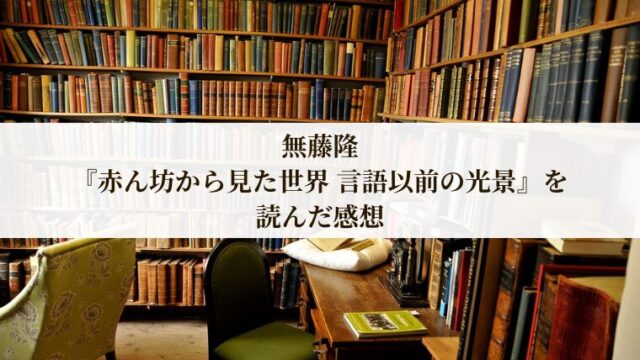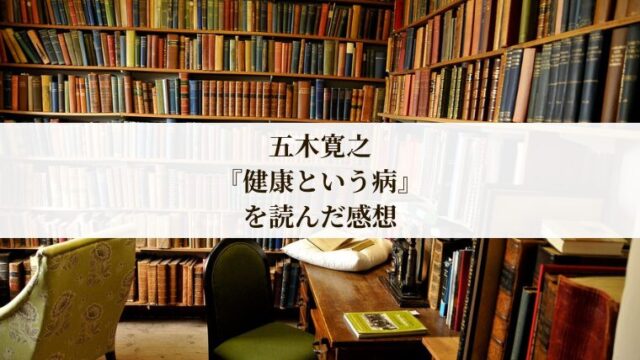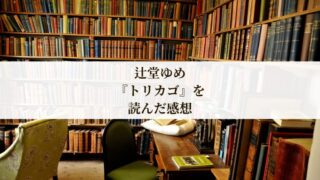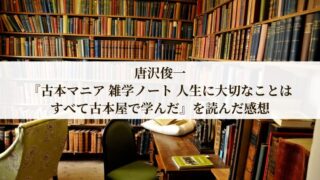フーベルトゥス・テレンバッハ『味と雰囲気』を読んだ感想

記事内に商品プロモーションを含む場合があります
皆様こんにちは、霜柱です。
ドイツの精神医学者、フーベルトゥス・テレンバッハ(Hubertus Tellenbach)の『味と雰囲気』(宮本忠雄/上田宣子・訳、みすず書房)を読みました。
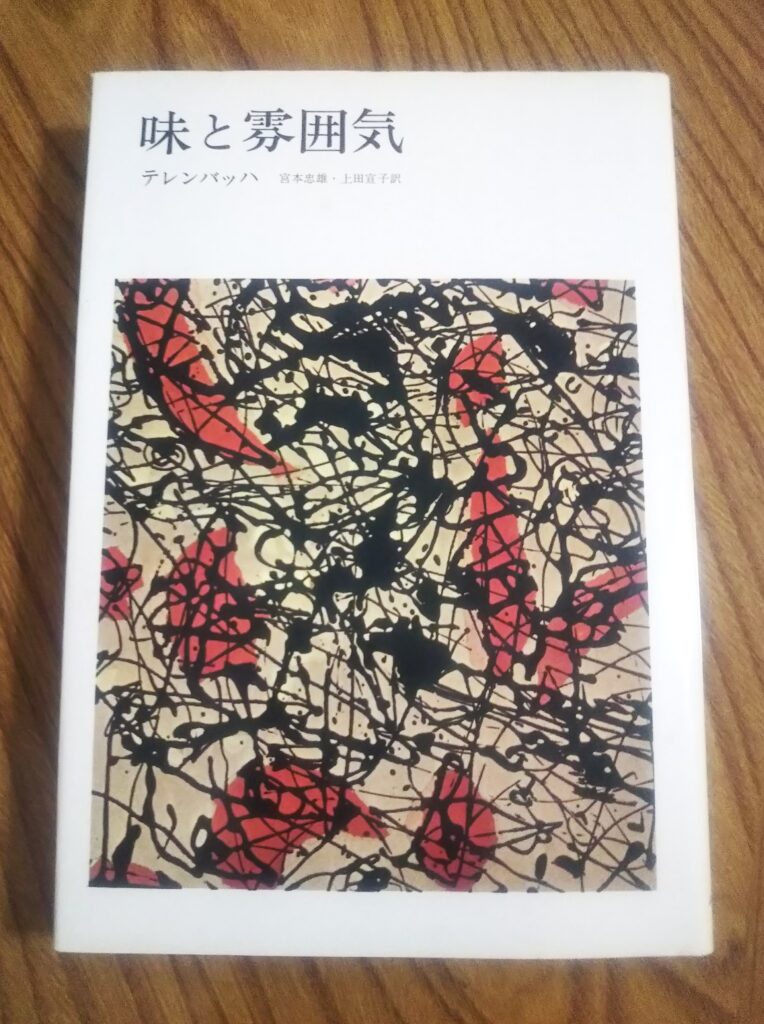
今回はこの本を読んだ感想を書いていこうと思います。
感想
専門的で難しい・・・
かなり専門的な内容に感じました。哲学とか心理学に詳しくないと読み進めるのに大変な気がします。言い回しも凝り過ぎていて傾向があるので、ただひたすら私は「???」でした(笑)。
0.1%も理解出来なかったと言って良いでしょう・・・。
内容は・・・
主に口腔感覚と匂いについて書かれています。
嗅ぐ事の支配性だとか、口腔感覚は近さの感覚だとかが書いてありましたが、よく分からず(笑)。
後半に差し掛かるとメランコリーや自己臭恐怖という病気と、それに罹った患者の症例の紹介と分析が載っていました。
他にドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』、ストリンドベリの『女中の子』に登場する人物の心理なども書かれています。これらの本を読んだ事がある方なら、もしかすると興味深く読めるかもしれません。
ただ、どちらにしても私はチンプンカンプンでした(笑)。
超簡単なまとめ
まとめを書く必要は無いかもしれまぜんが一応書きます。
臭いや雰囲気(東洋だと「気」に当て嵌まるらしい)から、人の心理や行動を分析して、書かれているので、そう言うのにかなり興味がある方なら読んでみると良いかもしれません。
ただ、既に書いた様に事前に心理学や哲学を知っておいた方が良いでしょう。
リンク
お読み頂きありがとうございました。ブログ村に参加しています。![]()
にほんブログ村