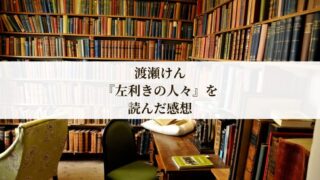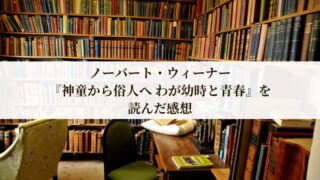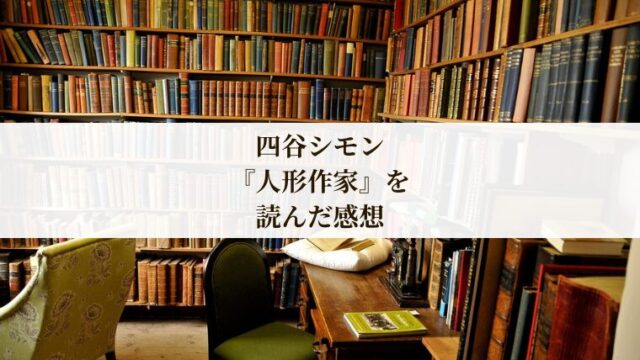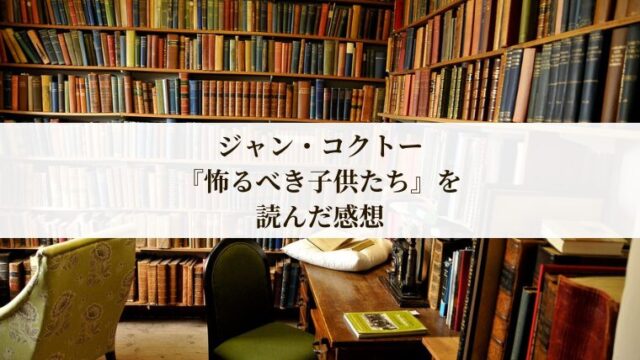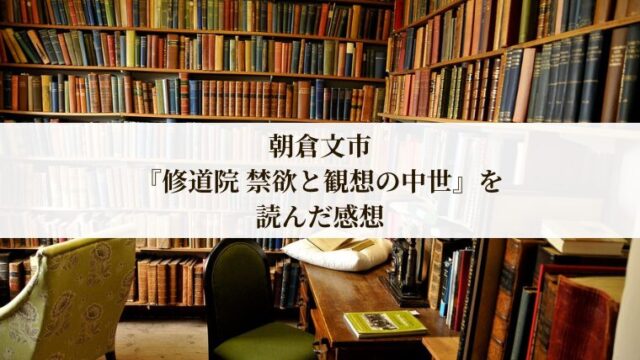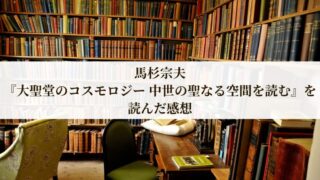中村義作『マンホールのふたはなぜ丸い? 暮らしの中の数学』を読んだ感想
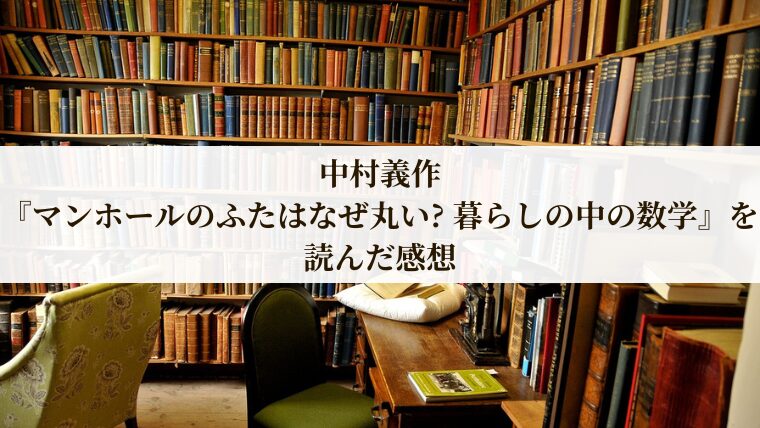
皆様こんにちは、霜柱です。
中村義作さんの『マンホールのふたはなぜ丸い? 暮らしの中の数学』(日経ビジネス人文庫)を読みました。
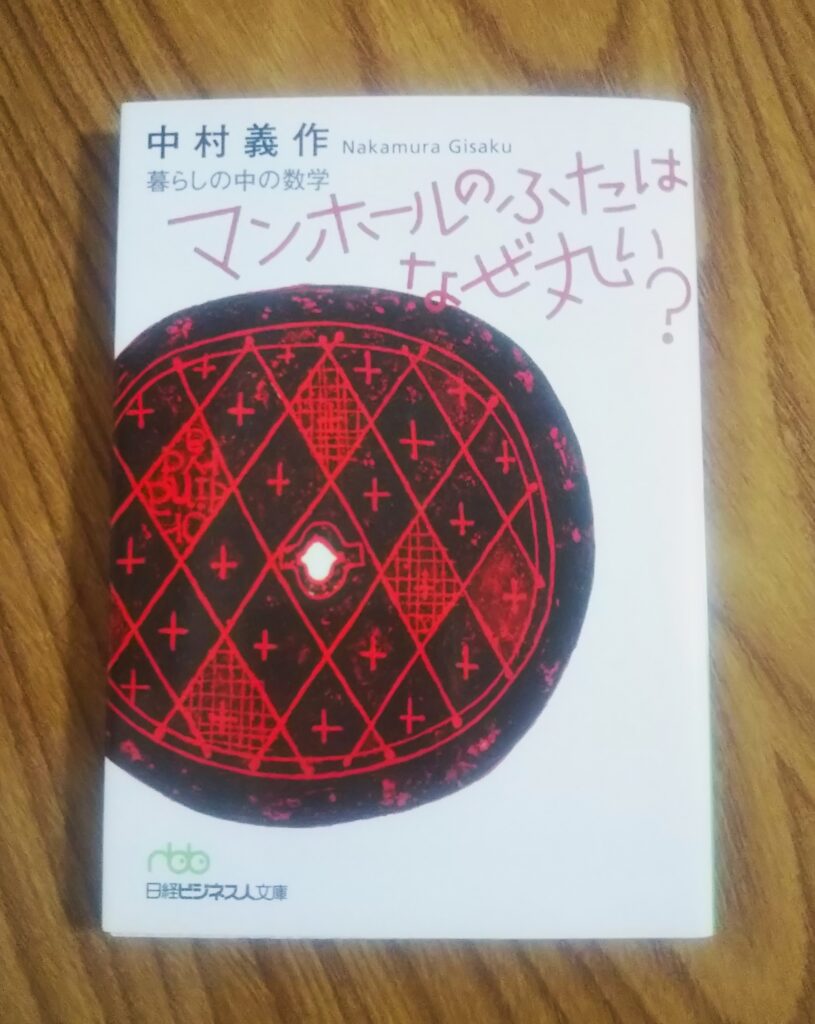
今回はこの本を読んだ感想を書いていこうと思います。
感想
身の回りには数学の真理が色々ある
本書のタイトルは『マンホールのふたはなぜ丸い?』ですが、他の物も沢山出てきます。というよりマンホールはむしろその中の1つで、特別にこれだけにページを割いている訳ではありません。
48のあらゆる事物を取り上げています。どれも身近でありながらも、しっかり思考したり観察した事が無いものばかりでした。
もしかすると、本書に載っていない事物でも、数学的な真理が使われているかもしれないですね。
印象に残った事物
どれも「へー!」と言いたくなる事物ばかりでしたが、その中で印象に残ったのを書きます。
- 丸いマンホールのふたは落ちる心配が無い。何故ならどこから測っても直径は同じだから。
- 約23人が集まると同じ誕生日の人がいる確率は五分五分になる。
- フィボナッチ数列は菊やヒマワリの花びら、松かさやパイナップルの実などから観察される。
ビックリしたのは誕生日の話です。約23人だけで同じ誕生日の人がいる確率が50%だなんて思いもしませんでした。1年は365日なので、もっと人数が必要だろうと予想していたので意外でした。
あと、「この中で違っている図形はどれか?」という問題がありました。1~3問目までは分かりましたが、4問目が難しかったです。答えを読んだ時は素っ頓狂な声で「そう考えるんだ!」と出しそうになりましたが、人によってはもしかしたら屁理屈に感じるかもしれない・・・。
そういえば、昔は三角形の牛乳パックを見かけた気がしますが、最近は全然見かけないですね。
簡単なまとめ
本書には身の回りの物を数学的に分析した事が書かれています。数学と言う言葉を聞いただけで「あっしは数学が苦手で・・・ごめんなすって」と敬遠する方がいるかもしれませんが、数式は出て来ないので大丈夫です。
分かりやすく説明しているので気楽に読む事が出来ます。それだけでなく、雑学本としても有用ですね。
数学が得意な方も苦手な方も楽しめる内容に仕上がっていると言えるでしょう。