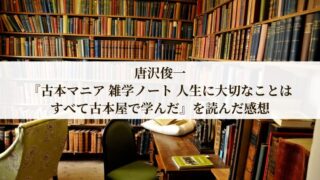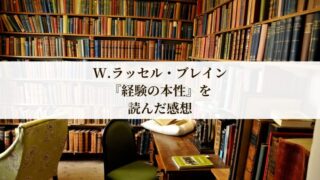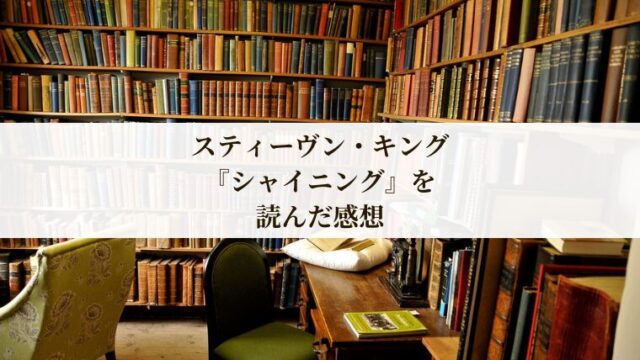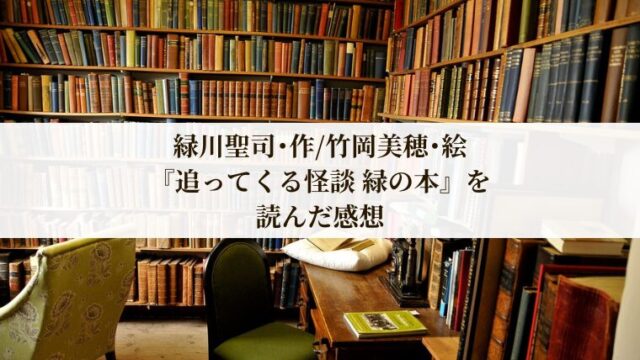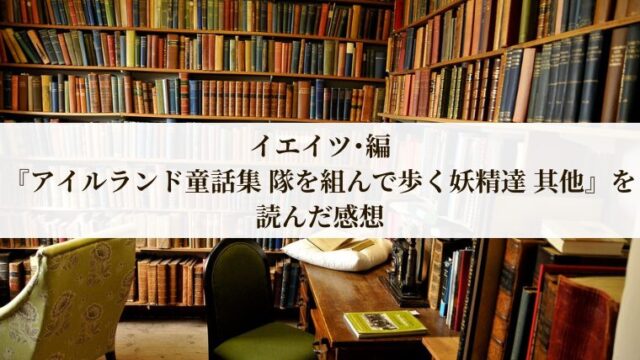外山滋比古『異本論』を読んだ感想
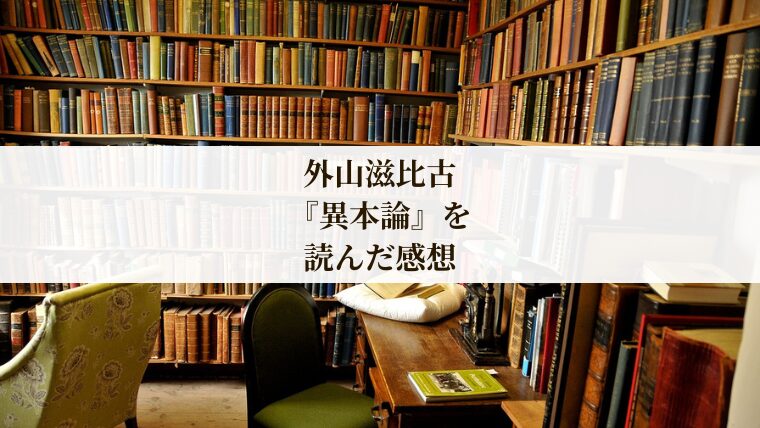
皆様こんにちは、霜柱です。
外山滋比古さんの『異本論』(みすず書房)を読みました。

今回はこの本を読んだ感想を書いていこうと思います。
感想
異本についての広範な考察
まず、そもそも異本って何なのでしょう?分からなかったので、辞書を引いてみました。
①いっぷう変わったところのある珍しい本。珍本。
集英社 国語辞典
②もと同一の内容であった書物が、写し替え伝えられている間に、文章・文字などが変化し、普通に使われているものと異なった本。
本書の場合は②の意味ですね。
海外の作品の日本語訳、古典の現代語訳、内容の編集などは異本となります。
ただ、それだけでなく個人の作品の捉え方の違いも異本に含まれるそうです。
色々と興味深い事が書かれていますが、後半になるに連れ、同じ事を言葉や表現を変えて書いている様に感じる部分はあった様な気がします。
しかし、それはあらゆる角度から異本について分析や考察をしたという事なのでしょう。
なので、異本という存在に興味をそそられましたね。
印象に残った言葉
本書は外山さんの異本に対する着眼点がとても光っており、その分印象に残る言葉も色々とありました。
以下、印象に残った言葉を幾つか引用します。
本という機械的コピーが多くなるにつれて、人間の理解をともなったコピーが少なくなってきたのは皮肉である。
異本は作品の生命の客観的相関物である。
雑誌編集は社会的、空間的異本化である。
他にも「その様に捉えるのか!」と思う文言はありました。
あと、移動についての考えもとても興味深かったです。
移動は物理的移動、動物的移動、植物的移動の3種類があり、外国文化の移動・摂取は植物的移動だそうです。よく分かる様な分からない様な(笑)。
ここまで異本について語る事が出来ると言うのは、それだけ外山さんが異本に関心があるだけでなく、異本という存在が私達の生活に密接に関わっている、という事を伝えたいのかなと感じました。
簡単なまとめ
本という存在の変化に興味がある方なら、本書を夢中になって読み進める事が出来ると思います。
私は異本について考えた事はこれっぽっちもありませんでした。ですが、本書を読み終わった時、自分の家にある本を軽く眺めて「殆どが異本なのかな? いや、もしかしたら全て異本かな?」と考えたりしました。
全く同じ内容の本でも単行本、文庫本、電子書籍など、媒体を変えて読んだら別の感想になる可能性もありそうです。
本書を読んだら、「この本はどの様にして異本化されたのだろう?」と考えてみるのも面白いかもしれません。